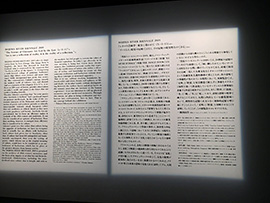森アーツセンター「バスキア」展 2019.9.21(土)~ 11.17(日)
現代美術の文脈からは外されがちなバスキアだけど、そんなこととは関係なく昔から好きだったなぁ。バスキアの絵は何かホッとするというか、生身の人間そのもののような親近感がある。今回の展覧会は点数も多く、結構見ごたえがあった。
そういえば、ジュリアン・シュナーベルの「バスキア」(1996)もよかった。デヴィッド・ボウイがウォーホルをやっている。ジョン・ケイルの「ハレルヤ」にもしびれた。




現代美術の文脈からは外されがちなバスキアだけど、そんなこととは関係なく昔から好きだったなぁ。バスキアの絵は何かホッとするというか、生身の人間そのもののような親近感がある。今回の展覧会は点数も多く、結構見ごたえがあった。
そういえば、ジュリアン・シュナーベルの「バスキア」(1996)もよかった。デヴィッド・ボウイがウォーホルをやっている。ジョン・ケイルの「ハレルヤ」にもしびれた。




塩田千春は今まで結構見ているし、今更どうなのかなぁと思いながら友人に誘われるまま見たけどやっぱ、すごかったです。
作品がすごいのは前から知っていたけど、今回は彼女の生身のセンシビリティに触れた気がしました。
塩田の関心は精神(魂)と肉体(身体)、内面と外界の乖離と融合にあるように感じた。その感受性が鋭すぎて、作品としてなんとかしないと自分が崩れてしまう、そんな切羽詰まった怖さまで感じさせます。だから内や外、またその境界となる血液、骨や皮膚、糸、土や窓などをモティーフとして、それを自分の身体を通してどうにか外(他)と繋ぎ合わせられないかと苦闘することが作品になっていると解釈しました。特にドイツ留学中のアブラモビッチやレベッカ・ホーンに師事して模索していた頃のパフォーマンスは、その希求が真っすぐで、無防備で文字通り体当たりで痛々しいほどです。
今まで完璧に出来上がったインスタレーションしか見てなくて、やっぱ天才だなぁとか思うだけだったけど、涙ぐましい格闘の軌跡を見た後の今回の結論としては(すごく当たり前で陳腐な表現になってしまうけど)、天才的な作品とは、身を切る痛みの果てにしか実現できないものだということでした。








[堂島リバービエンナーレ2019]に行って来ました。
サブタイトルが「シネマの芸術学 -東方に導かれて- ジャン・リュック=ゴダール『イメージの本』に誘われて」
ゴダールの最新映画作品『イメージの本』を基に、「私たちに未来を語るのは“アーカイブ”である」「アートとは、現実の反映ではなく、その反映の現実性なのである」と語る彼のコンセプトに沿って、アーティスティック・ディレクターの飯田髙誉がキュレーションしたもの。出品者はゲルハルト・リヒター、トーマス・ルフ、佐藤允、空音央、アルバート・トーレンなど。
ゴダールの「イメージの本」は、ほぼ全編既存の映画作品の断片を引用コラージュした作品。画像が劣化していたり極彩色であったり、くるくる場面が変わったりしてどこか意識の反映的(?)。ゴダールについて無知な私にはほとんどわからなかったけれど、会場配布のハンドアウトと交互に見て何とかついて行った。
リヒターは自作の構想や写真などで構成した「アトラス」。台紙の数が全部で圧巻の809枚。他、佐藤の油彩の他は写真や映像作品。もっとも面白かったのがフィオナ・タンの写真と映像作品。《人々の声 東京》という写真の作品は、東京で暮らす人々が自分たちを撮った写真(結婚式とか、日常風景だとか)を、持ち主から借りて背景情報なしでタンが選んで並べたもの。何ともよかった。写真に写っているのが誰だかわからないので、変な意識の誇張や理論が消えてなくなる。そこには単なる人生のある瞬間だけが素朴に純粋にあって、そこから人生は愛すべきものだということがひしひしと伝わってきた。